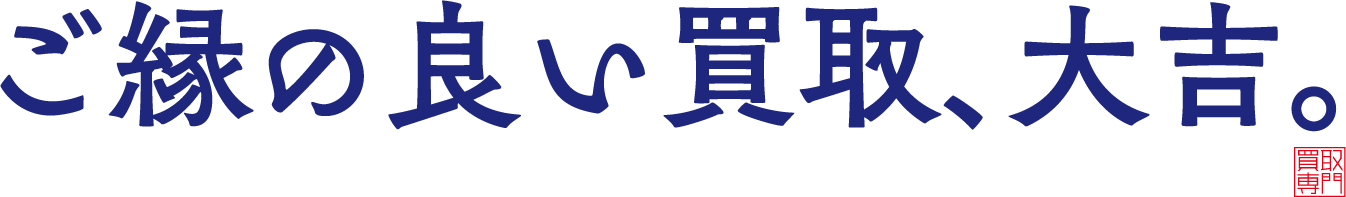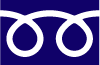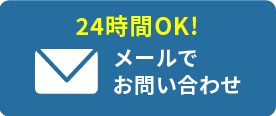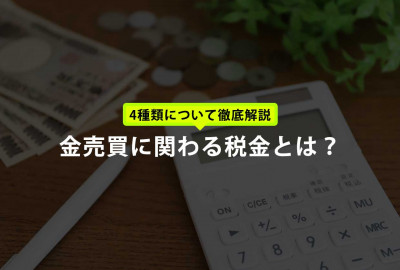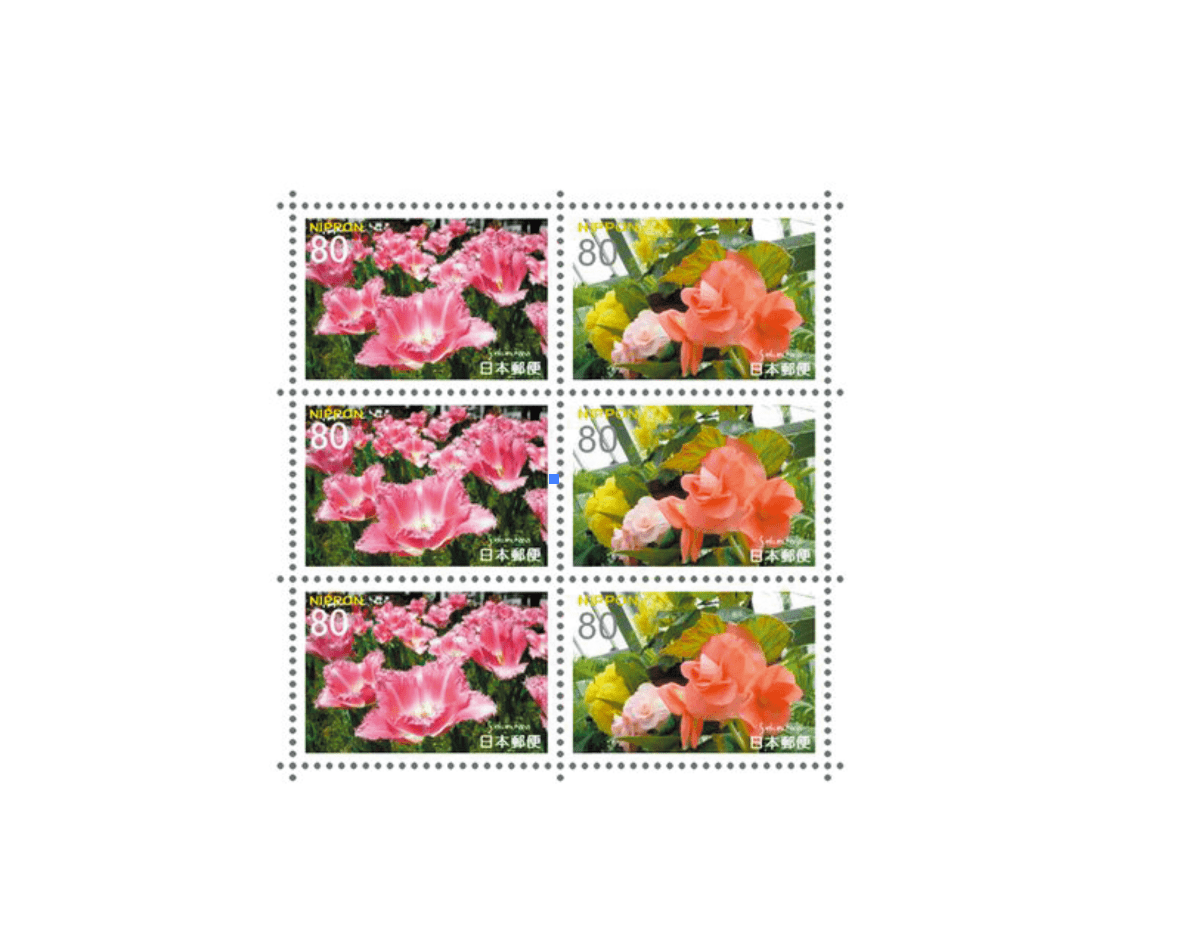金の売却時にかかる税金
金地金(インゴット)や金貨を売却して利益が出れば、当然ですが税金がかかかります。金地金はまた、売却まで保有していた期間の長さなどによって税金のかかり方が変わります。税金は投資には付きものの大きなコストの一つで、金地金に絡む税金は国税の監視も強まっています。高値で売却することだけを考えず、税金も含めたトータルのコストをしっかりと意識したいですね。
個人が金地金や金貨の売却で得た利益は原則、「譲渡所得」とされ、確定申告して所得税を支払う必要があります。ここで、利益は「売却金額−(購入金額+売却費用)」で計算しますが、譲渡所得には年間50万円までの特別控除があるため、利益が50万円以内なら申告は不要です。つまり、利益のうち50万円を超えた部分が課税対象で、給料など他の所得と合算して総合課税される仕組みです。
まず、挙げられるのが「譲渡所得」です。所有していた金を個人取引として売却した際に該当する所得区分で、金を買取に出した場合はほぼこの所得区分に該当します。この「譲渡所得」に関しては、金取引の他にも「土地」「建物」「株式」などのような、事業外の資産に該当されるもの。基本的に個人の投資として収入を得た場合は、譲渡所得へと分類されるのです。雑所得とは、個人が継続的に金を売却して収入を得ている場合に該当する所得区分です。定期的に金を売却していたり、長期間継続して金を売却していたりする場合は、雑所得に該当する場合があるため注意してください。
金の売買を個人ではなく「事業」として行い、利益を得ていた場合は「事業所得」に該当します。事業の業種に制限はなく、小売業やサービス業、卸売業など基本的にどのような業種であっても、事業として金を買取に出した場合は「事業所得」であるため、個人取引以外は事業所得として申告しなければなりません。金を買い取ってもらった際に得た利益は、課税対象となるため、適切な額を税金として納める義務があります。そして、具体的な計算方法は、ケースによって異なるため自身の状況を把握したうえで行うことが大切です。
まず、税金を計算するにあたり、確認しておきたいのが「所有期間」です。税金の計算方法は、金の所有期間によって異なるため注意しましょう。所有期間に関しては、大きく2つに分けることができ、「所有期間が5年以内」「所有期間が5年以上」で計算方法が異なります。
消費税の場合
金を購入する際は購入金額×消費税を国に納める義務生じます。金を売却する際は金を買い取る側が消費税を負担することになっています。もし金の価値が変わらなかったとした場合、金を購入した際の消費税が売却するときに上がっていたら、買い取り業者が消費税分を上乗せして買い取るということになります。購入した時よりも高い金額が手元に戻って利益が出る仕組みです。逆に消費税が下がったとしたら、購入した時よりも低い金額で売却することになります。金は、軽減税率の対象ではありません。そのため、金を購入する際には、10%の消費税が加算されます。たとえば、1万円分の金を購入したい場合は11,000円、10万円分の金を購入したい場合は11万円の支払いが必要です。金の購入金額が高ければ高いほど、より多くの税金を支払うことになります。消費税の納税義務者は、消費者ではなく事業者ですが、消費税は納税義務者と実質負担者を別にすることで税負担の水平的公平を図る「間接税」という扱いになるため、消費者が消費税を負担するよう求められています。消費税が金の売却に関係するケースは上記以外ではありません。
所得税の場合
次は、金を売却する際にかかる所得税についてです。どんな場面で課税対象となるのでしょうか。金を一般的な方が売却する場合は譲渡所得という区分の対象となり、課税の対象になります。譲渡所得は、さらに2パターンに分けられます。「購入から5年以上経過」して売却するケースと「購入から5年未満」の時に売却するケースでは税金を支払う金額等が変わります。購入して5年以上経過して売却する場合は、購入して5年未満のものを売却する際の課税譲渡所得金額の半分になります。つまり、購入から5年以上経過してからの売却のほうがお得ということになります。
相続税の場合
金を相続する際の相続税についてです。相続税とは、故人から親族などに受け継がれる財産の事です。金は相続財産として計算されます。なので、課税対象となります。相続税は遺産の「総額」に対して課税されるものであり、金も相続税の対象となります。金以外の遺産の総額、相続する人数によって課税される相続税は変わりますので、金のみを考慮した相続税額を正確に計算することは現実的ではありません。また相続税には基礎控除額があり、遺産総額が定められた金額を上回っていれば、上回った金額に対して相続税が課税されます。
所得別の考え方
譲渡所得の場合、譲渡所得で損失が出た場合、同一年の1月~12月の間で発生した譲渡所得の損失と利益を通算することができます。しかし、譲渡所得以外の損失の通算はできません。雑所得の場合、雑所得で損失が出た場合、譲渡所得のときと同様に、他の雑所得の損失と利益の通算が可能です。サラリーマンで給与収入が2,000万円以下で、その他の所得合計が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。事業所得の場合、事業所得で出た損失は、他の所得と通算できます。通算して純損失が残ってしまった場合、青色申告をすることで翌年から3年間は、所得金額から繰り越しで控除することや、前年への繰り戻し還付ができます。所有期間が5年を超す場合、金の所有期間が5年を超えている場合に売却で得た利益を「長期譲渡所得」といいます。譲渡益の出し方は短期譲渡所得と同じですが、長期譲渡所得で課税される金額は、短期譲渡所得の半分です。売る金が5年以下のモノと、5年を超えるモノが混ざっている場合、特別控除は5年以下の譲渡益を優先的に控除します。
金を売った金額が高額になったら税務署へ相談!
・金を売った場合は税金が発生することがある
・金を売った場合の所得には譲渡所得・雑所得・事業所得があり、それぞれ扱いが異なる
・金を売って損失が出れば通算が可能
・事業所得の場合、繰り越し控除や繰り戻し還付ができる
・金を売って大きな利益を得た場合、また、大きな損失を出した場合は納める税金が変わってくることがあります。
書類手続きなど手間がかかることが多いため、税務署へ相談するか、税理士などの専門家に任せるのが得策でしょう。
例外もあります!
ここ数年、金価格は上昇していることから、手持ちの金地金や金貨を売却して、譲渡益を得る方も多いと思われます。金を売却した場合の確定申告のときの税金の取扱いについてご説明をいたします。金地金や金貨を売却した時は、一般のサラリーマンなどの個人の方が譲渡した時には、譲渡所得として扱われ、給与などの他の所得と合わせて総合課税の対象になります。一方、営利を目的として継続的に金地金の売買を行っている場合には、その実態により雑所得又は事業所得として扱われます。また、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、金融類似商品の収益として扱われ、一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉徴収だけで課税関係は完結します。
まとめ
金売却時にはどんな税金がかかってくるのか、税金別にお話ししました。税金の種類ごとに複雑な計算があり、とても自分で計算するのは大変です。必要に応じて弊社査定員に相談するなどの対応をしてみてください。金の売却における税金は複雑なイメージがありますが、実は意外にもシンプルです。課税対象になる利益と、「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」について大まかに把握していれば、あとは計算式に基づいて税金を算出するだけ。決して難しいことではありません。初めて金を売却する方は、知らずに脱税を犯さないためにも、本ページで税金について理解を深めることが大切です。正しく税金を納めつつ、損をしないためにも、金の税金について正しい知識を得ておきましょう。