錬金術とは
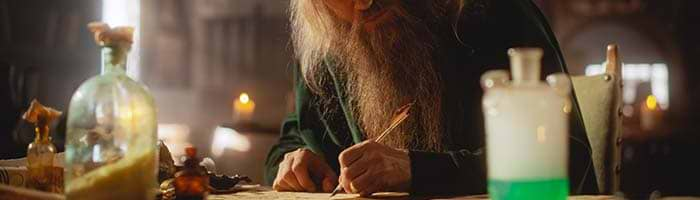
「錬金術」とは、化学的手段を用いて卑金属から貴金属を精錬しようとする試みのことを言い、鉱石から金属を作り出そうとしていました。実際は「合金」という物質を作り出す技術なのです。
化学変化が神秘に満ちていた古代社会においては、鉛などの卑金属を変性させて金をつくることを本気で考えた人々が現れています。
古代から十七世紀までの二千年近くものあいだ、錬金術はとても栄え、同時に人類の夢でもあったのです。
錬金術の起源
錬金術の起源は古代エジプトや古代ギリシアにあります。錬金術は、ヘレニズム文化の中心であった紀元前のエジプトのアレクサンドリアからイスラム世界に伝わり発展しました。
アリストテレスら古代ギリシアの哲学者の物質観は、中世アラビアの錬金術に多大な影響をもたらし、12世紀にはイスラム錬金術がラテン語訳されてヨーロッパで盛んに研究されるようになりました。
錬金術の試行の過程で、硫酸・硝酸・塩酸など、現在の化学薬品の多くが発見され、同時に多くの実験道具も発明されたのです。17世紀後半になると錬金術師でもあった化学者のロバート・ボイルが四元素説を否定します。
そのためアントワーヌ・ラヴォアジェが33の元素や「質量保存の法則」を発表することになり、これらの成果は現在の化学に引き継がれています。歴史学者フランシス・イェイツは、16世紀の錬金術が「17世紀の自然科学を生み出した」と話しています。
錬金術で金を作ることは可能か?
和歌山大学システム工学部精密物質学科の篠塚雄三氏によると、「錬金術は不老長寿の薬とともに、歴史が始まってからの人類の夢である。錬金術は物理や化学の進歩をうながし、不老長寿の薬は医学の発達につながりました。
不老長寿の薬を作ることはできるか、あるいは見いだすことはできるかどうかは現在のところ不明であるが、錬金術のほうは残念ながら不可能であることは明らかである。」と述べています。
この宇宙のあらゆる物質は、百種類あまりの原子の組み合わせからできており、たとえば金は金原子、鉄は鉄原子、食塩はナトリウム原子と塩素原子からできています。
したがって、いかなる化学反応をもってしても鉄原子を金原子に変えることはできない(理論上は可能であるが現実的に不可能)とされています。
ダイヤモンドで錬金術

原子をそのまま作り変えることは不可能ですが、原子はたった百種類あまりの組み合わせから、様々の物質が構成されています。それらがそれぞれ固有の性質をもち、この変化に富んだ宇宙を作っていることは、興味深いことです。
ということは、原子の新たな組み合わせを考えることで新しい物質を合成するという、形を変えた「錬金術」は可能となるのではないでしょうか。
地球の奇跡で誕生する「天然ダイヤモンド」
ではその中でダイヤモンドについて考えていこうと思います。
物質は温度によって固体、液体、気体の3形態をとり、低温では固体状態をとるのが普通である。固体状態では原子はなるべく近づき合って結晶構造を作っています。結晶構造の特徴とは、一言でいえば並進対称性、すなわち原子の規則正しい配列といえます。
ダイヤモンドの場合は簡単にいうなら炭素原子の集合体です。しかし同じ炭素原子の集合体として、鉛筆の芯の材料となる黒鉛も存在しています。世界一硬いといわれるダイヤモンドと、人の手でも簡単に折れてしまう黒鉛が、実は同じ炭素からできているなんて不思議です。
これは結合の仕方の違いによります。詳細な説明は省きますが、簡単にいうと「遙か昔に地球の内部の、非常に高圧のところで冷えて固まった炭素が、そのままの形で地上付近まで運ばれた時のみ」ダイヤモンドになるのです。
もちろん、様々な条件が奇跡的に重ならなければなりません。ひとつでも条件が欠けてしまえば、私たちの前にダイヤモンドとして姿を見せることはないでしょう。
人の手によって作りだされる「人工ダイヤモンド」
つまり、黒鉛に圧力をかければダイヤモンドができるということになり、実際のこのようにして人工ダイヤモンドを作ることは可能です。これこそ現代の錬金術であるといえるのではないでしょうか。
しかし、実際は高圧を作るのがむずかしく、今のところ小さい結晶しかできないため宝飾品としてはメモリアルダイヤなどの少ない用途でのみ活用されています。
もし将来、安価に大型の人工ダイヤモンドを作り出す技術を開発することに成功すれば、それこそ「金」を手に入れることになりそうです。貴重品としてのダイヤモンドの価値はなくなってしまうかもしれません。
まとめ
このように金やダイヤモンドを生み出すことによる錬金術は現実的ではないとわかります。ただ、こうした研究はエネルギー分野の発展には大きく貢献しています。
金を作るよりもっと価値のあるものが発見されたりしているので、無駄にはなっていないのです。しかし少なくとも、一般の私たちは、鉛を金に変える方法を考えるよりも、人生を金のような価値のあるものに変える努力をする方が賢明なようです。




